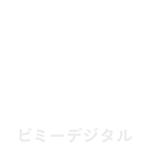-
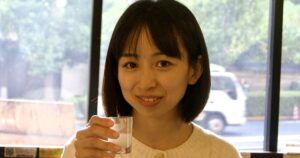
-
新企画「日本酒はお好きですか」
2026.01.28更新
【全国各地「蔵の味」を求めて旅をする】山内聖子
日本酒をこよなく愛する呑む文筆家が、地元でしか醸せない唯一無二の「蔵の味」を求めて全国各地の酒蔵へ旅する連載。記念すべき第一回目は、筆者が約17年前に名酒センターを通じて出会った、明治8年創業の「赤城山」(近藤酒造)を訪ねました。常に地元に愛される酒を目指してきた「赤城山」の魅力を紹介します。
近藤酒造(群馬県)

群馬へ行くと、いつも真っ先に「赤城山」を思い浮かべる。この酒は自分にとっていわば県境の入り口で、「赤城山」を飲まなければ群馬の日本酒旅は始まらないとすら思う。
群馬には「赤城山」を含む24ヶ所の日本酒蔵があり、他にも魅力的な酒はあるのだが、この酒を通過しないと群馬酒の郷に入れず、ベースをすっ飛ばしたような座りの悪さを感じて妙に落ち着かないのだ。

地元民にとっても「赤城山」は地酒のベースではないか。群馬をうろうろしていると、至るところで「赤城山」の文字が目につき、観光客向けの土産物屋だけではなく、地元の人たちが利用するスーパーやコンビニで買えるのが何よりの証拠。街の酒場でも「赤城山」はごく当たり前に飲める地酒の顔である。
地元に愛される酒を造りたい
“男の酒 辛口”
「売り先の約8割は地元です。いつまでも地元に愛される酒を造りたい」と6代目蔵元の近藤雄一郎さんは言う。

確かに、私にとって「赤城山」は名酒センターで馴染み深いが、都内ではほとんど見かけない。日本酒の消費が減少し続けている近年でも、全国トップの消費地である東京に目を向けるのではなく、いまだに地元で愛される地酒を貫く珍しい酒蔵なのだ。
そんな群馬を代表する地酒「赤城山」をここまで導いたのは、近藤酒造の定番である“男の酒 辛口”だろう。

きっかけは約40年前。先代の近藤新一郎さんが糖類などを加える三倍増醸造酒の製造をやめ、上質な日常酒だけを醸す覚悟を決めたことが転機となった。その強い思いは“辛口”に反映されている。
実は、かつての群馬は甘口の酒が好まれる傾向があり、もともと辛口タイプの酒を造っていた「赤城山」は長らく売り上げが苦戦。甘い三倍増醸造酒を造っていたのも、経営を立て直すための苦肉の策だった。
蔵の味の原点に
そんななかで、先代は蔵の味の原点に戻り、ラベルの見出しに“男の酒 辛口”と銘打った、吟醸酒と同じ精米歩合60%のキレある普通酒(現在は本醸造)を売り出した。すると、タイミングよくたまたま世間ではアサヒのスーパードライや新潟の淡麗酒などを中心とした辛口ブームが起こり、「赤城山」もようやく日の目を見ることに。

地元で徐々に辛口の酒として知られるようになり、群馬酒のトップブランドとしての地位を確立していく。だが、売れても安住せず、上質な日常酒を造るための試行錯誤をやめなかった成果は、今でも群馬で目にする「赤城山」の多さからもよくわかるはずだ。

麹米は全て手洗い
新たに武内太さんを杜氏に迎えた2023年からは、さらなる酒質の向上を目指し、製造工程の見直しに力を入れているという。
蔵元は言う。
「例えば、麹造りで使う米の洗い方です。今までは、吟醸や大吟醸のみ米を手洗いしていましたが、今は竹内杜氏の希望で純米酒や本醸造の米も全て手で洗っています。他にも自動製麹機(自動で米の品温管理ができる)を導入したり、搾った酒が出てくる蛇口のような先端部分を改良するなど、手間もお金もかかるのですが、こうした工夫は大事ですね。酒質が格段によくなるんですよ」

後味がさらにすっきりドライに
特に“辛口”などのレギュラー酒を飲めば、それがよくわかるだろう。酒の旨みがややシャープになり、後味がさらにすっきりドライに。


つまり「前よりもっと量が飲めます(笑)」と近藤さんは笑う。
その言葉通り、撮影時に開封した“辛口”は気持ちよく喉をすべり、ぺろっと快飲。あっという間に筆者の胃袋におさまった。
<筆者プロフィール> 山内聖子 呑む文筆家・唎酒師
1980年生まれ、岩手県盛岡市出身。22歳で飲んだひと口の日本酒がきっかけでライターの道へ。駆け出しの頃は浜松町時代の名酒センターでバイトしたことも。現在は酒にまつわることについて各媒体で執筆中。著書に『蔵を継ぐ』(双葉文庫)、『いつも、日本酒のことばかり。』『夜ふけの酒評 愛と独断の日本酒厳選50』『日本酒呑んで旅ゆけば』(共にイーストプレス)、『酒どころを旅する』(イカロス出版)、『BARレモン・ハート意外に知らない酒の基本知識』(双葉社)など。(2) Facebook